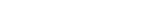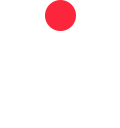-

- アテネ五輪競泳男子100メートル平泳ぎ決勝で金メダルの北島は雄たけびを上げガッツポーズ(2004年8月15日)
五輪では試合とともに、戦い終えた選手たちの第一声も楽しみにしている。人間をさらけだした、飾り気のない感情がむき出しになるからだ。だから時代に刻まれる名言が生まれたりもする。
心情をストレートに解き放った、有森裕子の「自分で自分をほめたい」や、北島康介の「ちょー気持ちいい」は流行語にもなった。ロンドン五輪の内村航平の「自分が自分であることを証明できた」は、世界王者としての誇りがにじむ名言だった。自己実現を達成した者たちの心の底からの叫びは、人の心を打つ。
リオ五輪が開幕して1週間。日本選手の言葉に、ある傾向が見える。自分のことよりも先に、支えてくれた人たちへの感謝の気持ちを語るのである。
金メダルを獲得した競泳の金藤理絵は「加藤コーチを信じ続けてきて本当によかった。家族だったり、加藤コーチの家族にも応援してもらった」と言った。金1号の萩野公介も「平井コーチに金メダルをかけてあげたい」と語っていた。この傾向は体操も柔道も同じ。過去の大会でも指導者や家族、仲間への感謝の言葉は多々聞かれたが、今大会は特別に多い。
東日本大震災の翌年に開催されたロンドン五輪は、吉田沙保里の「日本を元気に」の言葉に代表されるように、被災地を意識した発言が目立った。「勇気を与えられれば」の言葉のシャワーに少しうんざりした記憶がある。あの震災でスポーツ人たちは「スポーツの力」について真剣に考え、選手も多くの人に支えられていることを再確認させられた。ロンドンから4年、あのベクトルが、復興へと歩み始めた被災地から、より近い人に向けられるようになったということだろうか。
五輪の選手たちの言葉は時代を映す鏡でもある。
96年のアトランタ五輪では「楽しめました」の言葉が多く聞かれた。大会前、私は競泳の合宿取材で、メダル候補たちが不自然に「メダル」という言葉を口にしないことに困惑した。示し合わせたように「五輪を楽しみたい。自分なりのレースができれば」という言葉を並べる。期待や重圧を回避する口上のようで違和感を覚えた。80年代後半から五輪に商業主義が浸透し、メダル有望選手の注目度が一気に高まった。当時の選手にとって国民の期待は、想像以上の重荷だった。個人主義が台頭してきた時代。若者たちに「日本のために」は古くさくもあった。
その流れを変えたのが、98年W杯に初出場したサッカー日本代表だったと私は思っている。アジア予選での苦闘の連続に、国民は一喜一憂した。日の丸を背負って泥臭く走る選手たちの姿が、何とも格好良く見えた。そして、彼らは日本中の期待と重圧を、苦しみながらも見事にはね返してみせた。列島が熱狂に包まれた。若者たちには重苦しかった日の丸が、強い心の証しに見えたのかもしれない。
五輪にも新たな時代が到来した。04年アテネ五輪。競泳男子100メートル平泳ぎで金メダルを獲得した北島康介は、大会前から金メダル獲得を公言して、国民の期待と重圧を戦うエネルギーに転化してみせた。「ちょー気持ちいい」の第一声は、本当の意味で五輪を楽しんだ言葉だった。そして、当時まだ15歳だった卓球の福原愛。敗戦後の「楽しめましたか」の問いに、「楽しむために来たんじゃないんで、私は」。まるで強烈なスマッシュで打ち抜かれたように一同絶句。
五輪の選手たちの言葉には、人間とその生きざまがにじみ出る。と同時に、世相や時代まで描き出す。五輪のもう1つの見どころでもある。【首藤正徳】(敬称略)