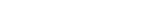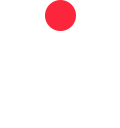-

- 選手に銅メダルをかけてもらうシンクロナイズドスイミング日本代表井村監督(中央)(撮影・江口和貴)
水面から空に向かって、脚が真っすぐに伸びる。一糸乱れぬ美しい一直線は、まるで芸術作品のようだった。2つの銅メダルを獲得したシンクロ日本代表の演技を見ながら、ふと思った。井村雅代ヘッドコーチ(HC)は芸術家なのだ。理想の作品に仕上がるまで、わずかなほころびも見逃さず、鋭いノミを入れ続ける。信念は寸分も揺らぐことがない。
妥協なき作品づくりは、1日10時間以上にも及ぶという。土台となる基礎づくりには特に心血を注ぐ。鬼と化し、鋭利な言葉をモリのごとく水中にグサグサと突き刺さして、選手が抱える限界の網を、手荒く引っ張り上げる。その選手の腰には重りが巻かれていた。この風景、昭和育ちの世代にはどこか懐かしい。汗と涙の猛特訓の果てにメダルを手にしたマーメイドたちの姿が、「東洋の魔女」と重なって見えた。
64年東京五輪で金メダルを獲得したバレーボール女子日本代表も、限界を超えた猛特訓で磨き抜かれた。大松博文監督の打つボールが嵐のごとく選手に襲いかかる。明け方まで続く妥協なき練習。選手の睡眠時間は3時間ほどだったという。休日は大みそかと元旦だけ。しごき、いじめの批判も浴びたが、「鬼の大松」は妥協しなかった。それが「東洋の魔女」の神話を光り輝かせた。
井村HCと大松監督。2人に共通する「鬼」「スパルタ」のイメージは的外れではない。だが、その哲学の芯にあるのは「あの娘たちに何とかメダルを」の無言の愛ではなかったか。可能性の扉を開いてあげるために叱る。つまり愛あるスパルタ。東洋の魔女たちは監督こそ理想の男性だったと口をそろえる。リオ五輪のデュエットで銅メダルを獲得した2人から井村HCは「誕生日のお祝いに」とメダルを首にかけてもらった。「私に怒られてもよくついてきた」の井村HCの言葉に、決勝のソ連戦を前に大松監督が選手にかけた「ワシの言うことを聞いて、よく頑張ってくれた」の言葉を思い出した。
大松監督の「オレについてこい」「なせば成る」は流行語にもなった。その指導哲学はスポーツ界にとどまらず、社会にも広がった。「アタックNO1」「サインはV」「柔道一直線」といったスポ根漫画が一大ブームとなった。いずれも猛特訓に耐え抜いた主人公が、頂点をつかむストーリーだ。教育ママが列島にあふれ、高度経済成長期の企業戦士の育成にもスポ根が利用された。そして、誤解した愛のない指導者たちの「体罰」や「パワハラ」が社会問題にもなった。
リオ五輪でシンクロ日本を復活させたことで、井村HCの指導哲学が脚光を浴びている。ただ「愛あるスパルタ」は誰もが実践できるものではない。選手の限界点を見極める眼力と、強い信頼関係と覚悟があってこそ力を発揮するのだ。この「井村式」が半世紀前と同じように平成の社会に広がったらどうなるだろう。考えると少し怖い。【首藤正徳】